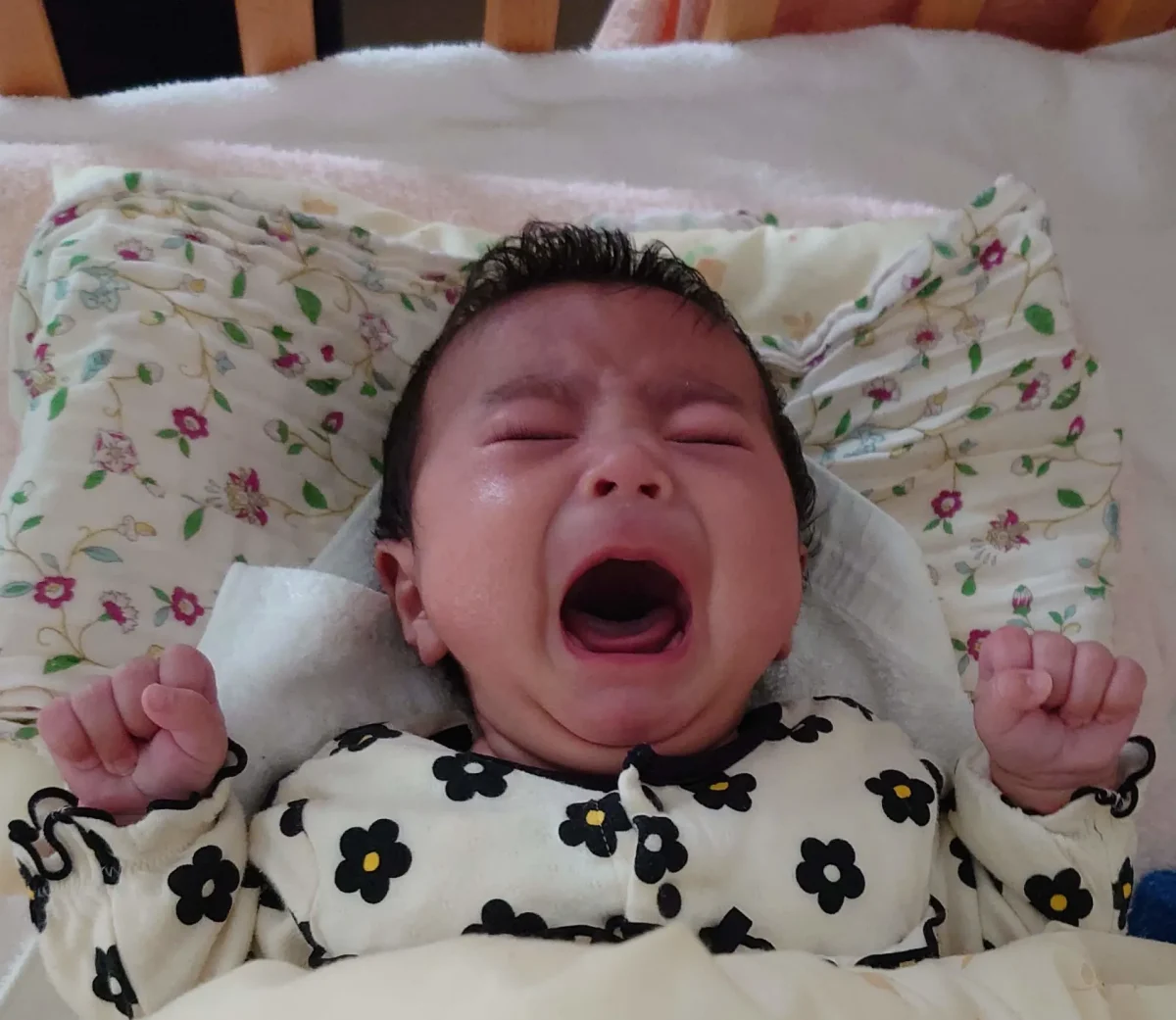夜泣きが続くと、食事や栄養が関係しているのではないかと考えることがあるかもしれません。
インターネットや育児書で栄養不足との関連について目にして、気になっている方もいるでしょう。
特に離乳食が進まない、好き嫌いが多いなど、食事面で心配がある場合は不安になるものです。
夜泣きと栄養不足には、どのような関係があるのでしょうか。
本記事では、両者の関係性と必要な栄養素について、詳しく解説します。
夜泣きと栄養不足の関係は?
夜泣きと栄養不足の関係は、栄養不足が直接の原因になることは稀ですが、間接的に睡眠の質に影響することはあります。
まず理解しておくべきは、夜泣きの主な原因は発達段階、生活リズム、情緒面の不安などであるということです。生後数ヶ月の赤ちゃんは、睡眠サイクルが未熟なために夜泣きをします。1歳前後では、分離不安や運動発達による興奮が原因です。2歳から3歳では、イヤイヤ期の情緒不安定が影響します。これらは発達の正常な過程であり、栄養不足とは直接関係ありません。
ただし、特定の栄養素が不足すると、睡眠の質が低下し、結果として夜泣きが増えることはあります。例えば、鉄分が不足すると、睡眠が浅くなり、夜中に頻繁に目が覚めることがあります。カルシウムやマグネシウムの不足は、神経の興奮を抑えにくくし、落ち着いて眠れない状態を引き起こすことがあります。これらは、栄養不足が夜泣きの直接的な原因というよりも、睡眠の質を低下させる要因の一つになるということです。
また、重度の栄養不足があれば話は別です。発展途上国などで見られる深刻な栄養失調の状態では、脳の発達や身体の機能に影響が出て、睡眠障害を含む様々な問題が生じます。しかし、日本のような先進国で、一般的な食事をしている場合、このレベルの栄養不足になることは極めて稀です。
つまり、夜泣きの原因を探る際、栄養不足だけに注目するのではなく、発達段階、生活環境、情緒面など、総合的に見ることが大切だということです。
では、どのような栄養素が睡眠と関連しているのでしょうか。
夜泣きに関連する可能性のある栄養不足
特定の栄養素の不足が、睡眠の質に影響し、間接的に夜泣きにつながることがあります。
鉄分不足
鉄分不足は、睡眠の質に最も影響を与える栄養素の一つです。鉄は、脳内の神経伝達物質の合成に必要であり、特にドーパミンやセロトニンの生成に関わっています。これらの神経伝達物質は、睡眠の調整に重要な役割を果たします。
鉄分が不足すると、夜間に脚がむずむずして眠れない「むずむず脚症候群」が起こることがあります。こどもにも起こりうる症状で、脚の不快感から夜中に何度も目が覚めて泣くことがあります。また、鉄欠乏性貧血になると、日中も疲れやすく、イライラしやすくなります。情緒が不安定になることで、夜泣きが増えることもあります。
鉄分不足の兆候としては、顔色が悪い、疲れやすい、食欲がない、集中力がない、爪がもろいなどがあります。血液検査で確認できるため、気になる場合は小児科で相談しましょう。
鉄分を多く含む食材は、レバー、赤身の肉、魚、大豆製品、ほうれん草などです。ビタミンCと一緒に摂ると吸収が良くなります。ただし、離乳食期は鉄分の摂取が難しいことが多いため、鉄分が強化された離乳食やフォローアップミルクの活用も有効です。
カルシウム・マグネシウム不足
カルシウムとマグネシウムは、神経の興奮を抑え、リラックスを促す働きがあります。これらのミネラルが不足すると、神経が興奮しやすくなり、落ち着いて眠れなくなることがあります。
カルシウムは、神経伝達や筋肉の収縮に関わります。不足すると、イライラしやすくなったり、寝つきが悪くなったりします。マグネシウムは、神経の興奮を抑え、筋肉をリラックスさせる働きがあります。不足すると、こむら返りが起きたり、眠りが浅くなったりします。
これらのミネラルは、バランスが重要です。カルシウムとマグネシウムは協働して働くため、どちらか一方だけを過剰に摂取するのではなく、バランス良く摂ることが大切です。
カルシウムを多く含む食材は、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品、小魚、豆腐、小松菜などです。マグネシウムを多く含む食材は、大豆製品、ナッツ類、海藻、バナナなどです。
ビタミンB群不足
ビタミンB群、特にビタミンB6とB12は、神経系の正常な機能に必要な栄養素です。これらが不足すると、神経伝達物質の合成がうまくいかず、睡眠の質が低下することがあります。
ビタミンB6は、セロトニンやメラトニンといった睡眠に関わる物質の合成に必要です。メラトニンは睡眠ホルモンとも呼ばれ、夜間の眠気を促します。ビタミンB6が不足すると、これらの物質が十分に作られず、睡眠リズムが乱れることがあります。
ビタミンB12は、神経系の健康維持に重要です。不足すると、神経の機能が低下し、睡眠障害を引き起こすことがあります。ただし、B12の不足は、動物性食品をまったく食べない場合を除いて、一般的には起こりにくいです。
ビタミンB群を多く含む食材は、肉類、魚類、卵、乳製品、全粒穀物、バナナなどです。バランスの良い食事をしていれば、通常は不足しません。
ビタミンD不足
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けるだけでなく、睡眠の質にも関わることが研究で示されています。ビタミンDの受容体は脳内にも存在し、睡眠の調整に関与していると考えられています。
ビタミンDは、日光を浴びることで皮膚で合成されます。しかし、日照時間が短い冬季や、日焼け止めの使用、室内で過ごす時間が長い場合などは、不足しやすくなります。近年、日本のこどもでもビタミンD不足が指摘されています。
ビタミンD不足の兆候は分かりにくいですが、骨の発達の遅れ、免疫力の低下、気分の落ち込みなどがあります。血液検査で確認できます。
ビタミンDを多く含む食材は、魚類(サケ、サバ、イワシなど)、きのこ類、卵黄などです。ただし、食品からだけでは十分な量を摂取しにくいため、日光浴も重要です。1日15分程度、顔と手を日光に当てるだけでも効果があります。
このように、特定の栄養素の不足が睡眠に影響することはありますが、すべての夜泣きが栄養不足で起こるわけではありません。
では、夜泣きの原因が栄養不足かどうかを、どう見極めればよいのでしょうか。
夜泣きの原因が栄養不足かどうかを見極める方法
栄養不足が関与しているかどうかは、いくつかのポイントで判断できます。
栄養不足の兆候チェックとしては、まず身体的なサインを観察します。顔色が悪い、疲れやすい、元気がない、成長曲線から外れている、爪や髪の毛がもろい、口内炎ができやすいなどの症状があれば、栄養不足の可能性があります。また、日中の機嫌や活動量も参考になります。栄養不足があると、日中もぐずりやすい、遊ぶ元気がない、すぐに疲れるなどの様子が見られます。
食事内容の振り返りも重要です。離乳食をほとんど食べない、特定の食品群(肉や魚など)をまったく食べない、極端な偏食がある、母乳やミルクだけで離乳食が進まないなどの場合は、栄養バランスが偏っている可能性があります。
ただし、こどもの食事には波があることも理解しておく必要があります。数日間食べない日があっても、その前後でバランスが取れていれば問題ないことが多いです。1週間単位で食事内容を振り返ってみましょう。
他の夜泣き原因との比較も必要です。夜泣きが始まった時期を思い出してみます。離乳食を始めた直後、特定の食品を食べなくなった時期と重なっているなら、栄養との関連があるかもしれません。一方、保育園入園、引っ越し、弟妹の誕生など、環境の変化と重なっている場合は、情緒面の影響が大きいと考えられます。
また、夜泣きの起こり方も手がかりになります。栄養不足による睡眠障害の場合、夜中に何度も目が覚める、眠りが浅い、寝つきが悪いなど、睡眠全体の質が低下します。一方、分離不安や悪夢による夜泣きは、特定の時間帯に激しく泣くなど、パターンが異なります。
医師への相談が必要な場合は、明確な栄養不足の兆候がある、成長が遅れている、極端な偏食がある、夜泣きに加えて日中の様子も気になるなどの時です。小児科で相談し、必要に応じて血液検査を受けましょう。鉄欠乏性貧血やビタミンD不足などは、検査で確認できます。
栄養不足が確認されれば、食事内容の見直しや、場合によってはサプリメントの使用などで対処できます。しかし、夜泣きの原因が栄養だけではないことも多いため、総合的なアプローチが必要です。
では、栄養面でどのような対策ができるのでしょうか。
夜泣き改善のための栄養面での対策
バランスの良い食事が基本であり、無理なく栄養を摂取することが大切です。
離乳食期の栄養バランス
離乳食期は、栄養バランスを整えるのが難しい時期です。母乳やミルクからの栄養が中心ですが、徐々に食事からの栄養も必要になります。
鉄分は、生後9ヶ月頃から不足しやすくなります。母乳やミルクだけでは十分な量を摂取できないため、鉄分を含む食材を積極的に取り入れましょう。レバーは鉄分が豊富ですが、食べにくい場合は、赤身の魚、豆腐、ほうれん草などでも補えます。鉄分が強化されたベビーフードも活用できます。
離乳食を食べない場合は、無理に食べさせようとせず、フォローアップミルクで栄養を補うことも一つの方法です。フォローアップミルクには、鉄分やカルシウムなど、不足しがちな栄養素が添加されています。ただし、普通のミルクや母乳の代わりではなく、あくまで補助として使用します。
食材の形状や調理法を工夫することも大切です。食べやすい大きさ、柔らかさに調理する、好きな味付けにするなど、こどもが食べやすいように工夫します。無理に食べさせるとかえって食事嫌いになるため、楽しい雰囲気で食事をすることを優先しましょう。
幼児期の食事の工夫
1歳を過ぎると、大人とほぼ同じものが食べられるようになります。バランスの良い食事を心がけましょう。
主食、主菜、副菜を揃えることが基本です。ご飯やパンなどの主食、肉や魚、卵、大豆製品などのタンパク質、野菜やきのこ、海藻などの副菜をバランス良く食べます。毎食完璧でなくても、1日や1週間単位でバランスが取れていれば問題ありません。
偏食がある場合は、無理に食べさせるのではなく、少しずつ慣れさせていきます。嫌いな食材を細かく刻んで好きな料理に混ぜる、調理法を変える、一緒に料理をして興味を持たせるなど、工夫してみましょう。ただし、食事が苦痛にならないことが最優先です。
夕食の時間帯も重要です。寝る直前に食事をすると、消化が睡眠を妨げることがあります。夕食は就寝の2〜3時間前までに済ませるのが理想的です。また、夕食に消化の良いものを選ぶことも、睡眠の質を高めます。
水分補給も忘れずに。脱水状態だと睡眠の質が低下します。ただし、寝る直前の大量の水分摂取は、夜中にトイレで目が覚める原因になるため、夕方までに十分な水分を摂るようにします。
サプリメントの考え方
サプリメントは、食事で補えない栄養を補助するものです。基本は食事からの栄養摂取であり、サプリメントに頼りすぎないことが大切です。
医師に栄養不足を指摘された場合や、血液検査で欠乏が確認された場合は、サプリメントの使用が推奨されることがあります。鉄剤、ビタミンDサプリメントなど、医師の指示に従って使用します。
一方、特に問題がない場合に、予防的にサプリメントを使用する必要は通常ありません。むしろ、過剰摂取のリスクもあります。脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は体内に蓄積されるため、過剰摂取は健康を害することがあります。
市販のこども向けマルチビタミンなどを使用する場合は、用量を守り、他の栄養補助食品との重複に注意します。また、サプリメントを使用していても、食事の改善努力は続けることが大切です。
このように、栄養面での対策は重要ですが、それだけで夜泣きが解決するとは限りません。
夜泣きには様々な原因があるため、総合的なアプローチが必要です。
栄養不足以外の夜泣き原因への対処
栄養だけに注目するのではなく、他の要因にも目を向けることが重要です。
発達段階による夜泣きは、最も一般的な原因です。生後3〜4ヶ月の睡眠リズムの確立期、8〜9ヶ月の分離不安のピーク、1歳前後の歩行開始期、2〜3歳のイヤイヤ期など、各発達段階で夜泣きが起こりやすくなります。これらは正常な発達過程であり、時間が解決することが多いです。発達段階に応じた適切な対応をすることが大切です。
生活リズムの乱れも夜泣きの大きな原因です。就寝時間や起床時間が不規則、昼寝が長すぎる、日中の活動量が少ない、夜遅くまで明るい環境にいるなどの問題があると、睡眠の質が低下します。規則正しい生活リズムを作ることで、夜泣きが改善することも多いです。
情緒面の不安も見逃せません。保育園への入園、弟妹の誕生、引っ越し、両親の不和など、環境の変化や家庭内のストレスは、こどもの情緒に影響します。日中にたっぷりスキンシップを取る、安心できる環境を作る、大きな変化がある時は特に配慮するなど、情緒面のケアが必要です。
睡眠環境の問題も確認しましょう。部屋が暑すぎたり寒すぎたり、明るすぎたり、騒音があったりすると、睡眠が妨げられます。適切な温度、湿度、暗さ、静けさを保つことで、睡眠の質が向上します。また、寝具が合っていない、パジャマが窮屈など、細かい点も影響することがあります。
総合的なアプローチの重要性を理解することが大切です。栄養面を改善しつつ、生活リズムを整え、情緒面のケアをし、睡眠環境を整えるという、多方面からのアプローチが効果的です。一つの要因だけに注目するのではなく、全体を見渡すことで、夜泣きの根本的な改善につながります。
また、夜泣きは必ず終わりが来ることを忘れないでください。今は大変でも、成長とともに睡眠は安定していきます。栄養面で過度に神経質になる必要はありません。
バランスの良い食事を心がけつつ、こどもの成長を信じて、焦らず対応していくことが大切です。食事を楽しい時間にすること、家族で一緒に食べること、こういった基本的なことが、結果的にこどもの健康と良好な睡眠につながっていきます。
監修

略歴
| 2017年 | 本田右志理事長より右脳記憶教育講座を指南、「JUNKK認定マスター講師」取得 |
|---|---|
| 2018年 | 幼児教室アップルキッズをリビングサロンとして開講 |
| 2020年 | 佐々木進学教室Tokiwaみらい内へ移転、「佐々木進学教室幼児部」として再スタート |
| 2025年 | 一般社団法人 日本右脳記憶教育協会(JUNKK)代表理事に就任 |